こんにちは!歯科衛生士のmonです!
子育て中、多くの保護者が一度は直面するのが「指しゃぶり」。赤ちゃんや小さな子どもが眠る前や不安なときに指をしゃぶる姿は、一見かわいらしく見えるものです。しかし、成長とともに「いつまで続くの?」「歯並びに悪影響はないの?」と心配になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、指しゃぶりが歯並びに与える影響や、やめるタイミング、やさしいサポート方法についてご紹介します。
指しゃぶりはなぜ起こる?

指しゃぶりは、赤ちゃんが生まれつき持っている吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)という本能的な行動です。母乳や哺乳瓶を吸うための機能として備わっており、眠いとき、退屈なとき、不安なときなど、さまざまな感情を落ち着ける自己安心行動(セルフコンフォート)の一つとされています。
実際、胎児の段階でエコーに映った赤ちゃんが指をしゃぶっていることもあり、非常に自然な行為なのです。
指しゃぶりはいつまで続く?
多くの子どもは成長とともに自然と指しゃぶりを卒業していきます。目安としては、2〜3歳ごろまでに頻度が減り、4歳頃までにはやめることが多いです。
ただし、5歳以降になっても日常的に指しゃぶりをしている場合は、習慣化している可能性が高く、歯並びや顎の発達に影響が出るリスクもあります。
指しゃぶりが歯並びに与える影響とは

指しゃぶりの頻度や力の強さ、指を入れる位置によって異なりますが、以下のような影響が起こる可能性があります。
① 出っ歯(上顎前突)
上の前歯が前方に押し出され、いわゆる「出っ歯」になることがあります。
② 開咬(かいこう)
上下の前歯の間にすき間ができ、かみ合わなくなる状態。奥歯だけで噛んでいるような感覚になり、食べ物がうまく噛めなかったり、発音に影響が出ることもあります。
③ 噛み合わせのずれ
上あごと下あごのバランスが崩れ、将来的に矯正治療が必要になるケースもあります。
やめさせるべき?それとも自然に任せる?
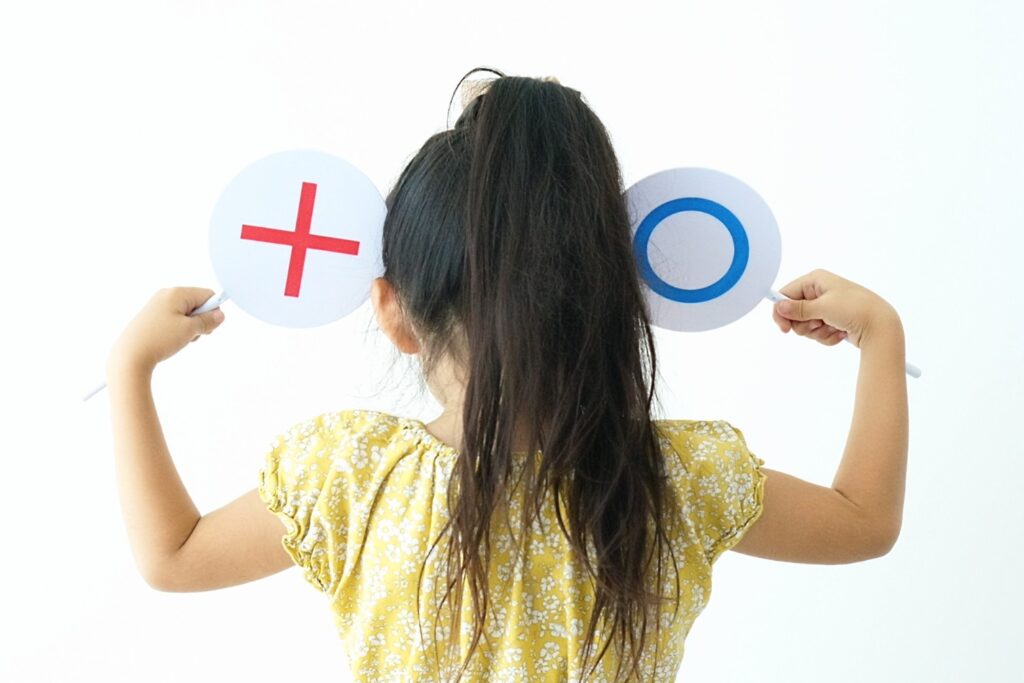
指しゃぶりは心の発達と深く関わっているため、無理にやめさせることは逆効果になることも。まずは「なぜしゃぶっているのか」を観察することが大切です。
たとえば…
-
不安や寂しさからくる安心行動なのか?
-
眠いときの習慣なのか?
-
退屈で手持ち無沙汰だからなのか?
理由を見つけたうえで、代替の安心材料(お気に入りのぬいぐるみや絵本)を用意するのも効果的です。
優しくやめるサポート方法
無理に叱ったり、手を引き離すと逆効果になることがあるので、以下のようなやさしい方法がおすすめです。
1. 声かけをして意識させる
「○○ちゃん、今指しゃぶってるよ〜」「おててあったかいね」など、やさしい声かけで本人が気づけるようにします。
2. 手を使う遊びを増やす
粘土遊び、折り紙、塗り絵など、手を使うことで自然と指しゃぶりの頻度が減ることがあります。
3. 絵本を活用する
「指しゃぶりをやめた○○ちゃん」など、やめるきっかけになるようなストーリー絵本を取り入れるのもおすすめです。
4. 成功を一緒に喜ぶ
「今日は指しゃぶりしなかったね!すごいね」と、できたことにフォーカスして褒めてあげましょう。
歯科医師に相談するタイミングは?
もし5歳を過ぎても指しゃぶりが続いていたり、すでに歯並びや噛み合わせに変化が見られる場合は、小児歯科や矯正歯科で相談してみましょう。
早期の相談によって、簡単なマウスピースで対応できるケースもあり、本格的な矯正を避けられる可能性もあります。
まとめ

指しゃぶりは、赤ちゃんの自然な行動であり、成長過程において心の安定に役立つ大切な行為です。ただし、年齢が上がっても続く場合は、歯並びや噛み合わせに影響を与えることがあるため、やさしく見守りながら少しずつやめる方向へサポートしていきましょう。
大切なのは、無理にやめさせるのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら前向きに取り組むことです。家庭での声かけや工夫と、必要に応じた専門家のサポートをうまく活用しながら、健やかな成長を見守っていきたいですね!
